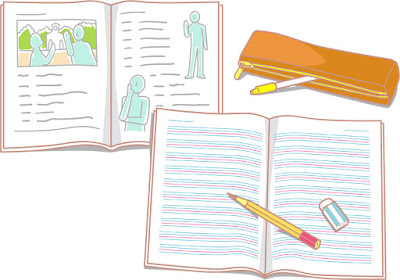一度は半分以上の授業が対面となり、賑わいをみせていたキャンパスが、今ではどんどん静けさを取り戻しているようになった。そんな議論が始まった4月24日(土)の夜に何か私にも出来ることはないのだろうか?ということで、Golden Week 特別企画と題して、「大学教員・先輩が歩んだ道」という連続セミナーイベントを企画した。最初に思い浮かんだのは、現在、大学で教えている学部1年生。折角、大学での勉強を楽しみにしてきた学生さんたちが、新型コロナウィルスという未知なる社会現象と対峙しなければならず、右往左往してしまっている姿はさすがに何か出来るのではないか?と考えた。セミナーシリーズのスピーカーは私の独断と偏見で選んだもので、「みんな違って、それでいい」というメッセージが何とか伝われば良いかな?という人選にしたつもりだ。すべて自分が築き上げてきた人脈で、今回のスピーカー陣があっという間に決まった。今回、協力できなかった方を含め、様々な方のご協力のもと、今回のスピーカーを集めることが出来たのだと思っている。この場を借りて感謝したい。更に、休憩中に何も「シーン」としているのが嫌だったので、メンバーの一人が友達で、最近インストルメントを中心に活動を始めた 陽kage の楽曲を使用させていただいた。また、事前に Zoom の接続チェックを友達としたり、友達に恵まれたなぁ。。。と思った2日間だったと思う。
一方、当初は Zoom のブレイクアウトルーム機能を使って、遠く離れた友達と仲良くなろうという企画を予定していたが、時間もなくて一切できなかった。こういうオンライン上での出会い場を創出する工夫は出来なかったと感じている。この点は反省しなければならない点だと思う。もし、ご覧いただいて、感想等ありましたら Google Form 上から投稿していただければと思う。
個人的には非常に密度の濃い2日間で、ドップリ疲れた。オンライン授業を受けている学生さんたちは、日々知らないことが出てくる授業を特に1年生などは朝から夕方まで受けていると思うと、ゾッとする。2日間で辛いのだから、週5日も真剣に人の話を聞き続けるのは難しいだろう。そんな中、日々の授業は続いていく。一大学教員として、この状況の中で何をすべきかということを考えさせられる。そんな中、本セミナーシリーズが皆さんの何かしらのヒント、きっかけになればと思っている。
5月4日(火)
1限目:北川 拓也 w/ 成川 礼, 鹿野 豊 [対談形式]
2限目:登 大遊
3限目:中田 陽介
4限目:髙山 晶子
5月5日(水)
1限目:平 理一郎 w/ 鹿野 豊 [対談形式]
2限目:成川 礼
3限目:道林 千晶
4限目:高田 修太